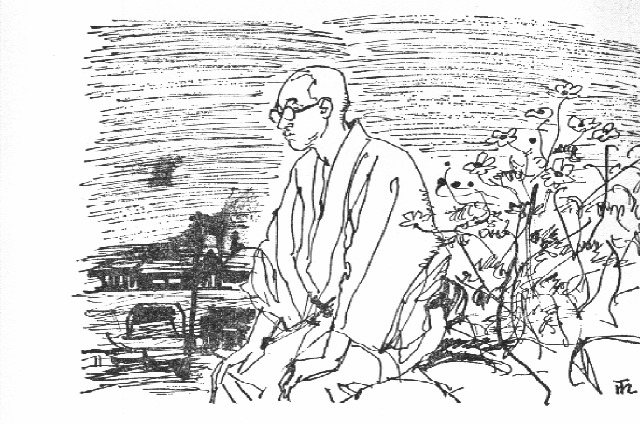
11.18の意義について
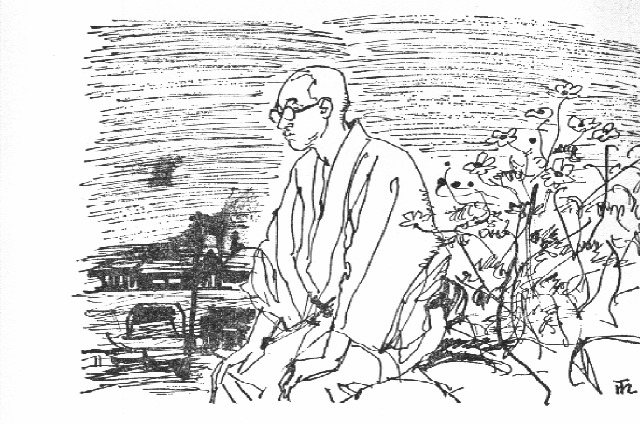
【経過】
①1930年(昭和5年)11月18日
牧口常三郎 創価教育学体系発刊
この日より、創価教育学会の具体的活動が始まる。この日を持って創価学会発足の日となる。
②1944年(昭和19年)11月18日
牧口常三郎初代会長、不敬罪並びに治安維持法違反の容疑で投獄中に、栄養失調による衰弱のため死去。享年73歳。
ほぼ同じ頃、獄中にて弟子戸田城外(後に城聖と改名)末法地涌の菩薩の後身を確信。広宣流布を誓う。
③1946年(昭和21年)11月17日
神田教育会館で故牧口常三郎初代会長三回忌法要執り行われる。同日午後、戦後第一回創価学会総会が同じ場所にて開催される。

【意義について】
1.創価学会の誕生日。
創価学会の前身は牧口常三郎初代会長の提唱した「創価教育学」を実践する教育者の集まりであった創価教育学会であった。
しかし、戸田城聖第二代会長は教育界に留まらず、経済、文化等社会の隅々まで日蓮大聖人の仏法を浸透させるために創価教育学会を発展的に解消させ、「創価学会」として新たなるスタートを切ったのである。
2.師弟共戦を確認する日。
戦中の思想弾圧の流れはついに創価教育学会をも飲み込んだ。1943年(昭和18年)7月に牧口会長、戸田理事長を始め幹部21人の逮捕と言う形で現れたのである。
そして、1年あまりの過酷な獄中生活は、牧口会長を獄死へ、戸田理事長を満身創痍の病人へと追いつめる結果となった。
しかし、牧口会長の獄死は、其の弟子である戸田第2代会長への確信に姿を変え、出獄後の「創価学会」への変革並びに日蓮正宗の古今未曽有の発展へとつながっていったのである。