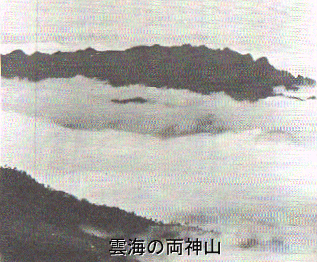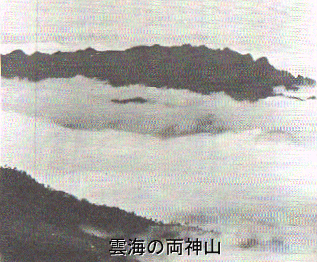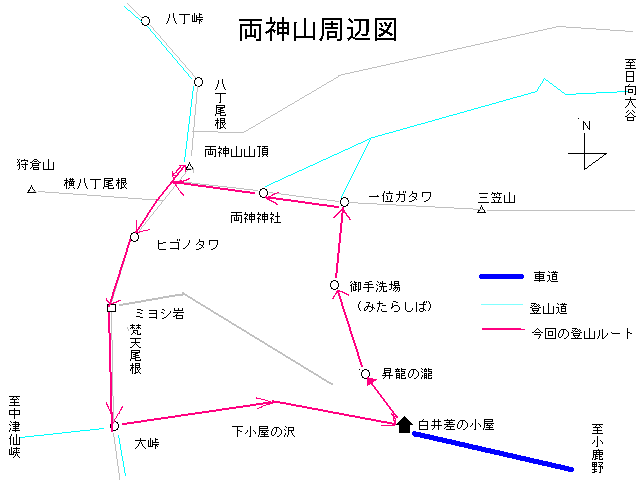両神山山行記
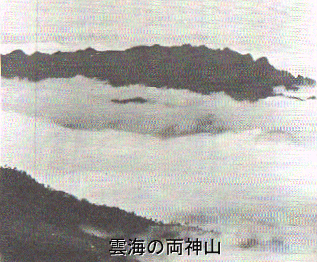
両神山は埼玉県の西部、秩父郡両神村と大滝村の境にそびえる、標高1724メートルの山である。岩峰険しく、鋸を思わせるその姿は周囲にある奥秩父の山や、奥武蔵・西上州の山とは異なり、敬虔な思いさえ抱かせる存在の山である。
伝説によれば、かの倭建命(日本武尊)が東州征伐のおり、この山を目印にして八日間旅を続けたことから「八日見山」(ようかみやま)とよばれ、それがなまって「両神山(りょうがみやま)」とよばれたという。言われてみれば確かに、北関東から見える山の中では特徴ある数少ない山の一つである。
私は以前より、奥武蔵の武甲山、上越国境の谷川岳とともに、一回は登ってみたい山のひとつに数えていた。武甲山はすでに1993年の10月に訪れている。次はこの「両神山」だと心ひそかに決めていた。
両神山へ訪れるルートは、大きく分けて二つある。東側に延びる尾根を挟んで北側から登る日向大谷口(ひなたおおやぐち)と、南側から登る白井差口(しろいさすぐち)である。私は比較的登る距離が短い白井差口から登ることにした。
11月6日の早朝、まだ夜が明けぬ午前4時半に家を出発した私は、車で両神村白井差の山小屋をめざした。秩父・小鹿野町を抜けて両神村に入り、白井差小屋の前に到着したのは午前5時半。すでに空は薄明を迎え、山々は紫色に染まってみえた。紅葉も麓まで下りていて色鮮やかに。1993年11月6日(土)の天気は雲一つない快晴。まさに、絶好の登山日和であった。
白井差の小屋の前には駐車場というものはなかったが、道が行き止まりの状態なのでその道の片隅に車を止めた。既に何名かの入山者があるようで、車も2・3台はあったろうか。それでも、あと数台は止める余裕はある。ここに置いても邪魔にはならないようだった。
今回の山行の目的は二つある。一つは自分の趣味の一つである、アマチュア無線の移動運用。それに、前から憧れていた両神山の散策である。人づてに両神山の素晴らしさは聞いてはいたが、自分の目で見、肌で感じてみたかったのである。ところが実は、この2つがくせ者だった。詳細は後に述べるが、失敗の一つはここに存在していたのである。
両神山にはクサリ場が多い。人づてに、さらに両神山を紹介している文献にもそれは載っていた。だから私はこのとき、両手を常にフリーに出来るように、いつもなら無線のアンテナを移動用のアンテナポールに括り付けていたのを、すべてリュックに括り付けることにした。これによって両手はフリーになった。さらにそれまでの山では素手で登っていたが、今回からは滑り止めのついた軍手を用意。運転用の薄手袋のうえに軍手をはめることにより、クサリ場対策とした。これが後に非常に役に立った。
持ち物は50MHz用無線機1台。50MHzと430MHzの移動用アンテナ。12Vのバッテリー、同軸ケーブルその他食料、雨具を含めて20Kgにもなった。これはかなりの重量だった。しかし、背負ってみるとたいしたことはない。この程度ならゆっくりと登れば良いのだから。だから家も早く出て余裕をみた。3倍時間を掛けても余裕で下山できる行程である。私は文字通り高(たか)をくくったのだ。
準備には時間を掛けた。既に朝日は昇り、山々を照らし出している。すでに予定は狂い始めていた。予定では6時に登山開始としていたが、6時半を回っていた。そんなに急ぐことではない。3時間もあれば余裕であると踏んでいた。もし遅れても頂上にいる時間を削れば良いと思っていた。このように予定に対して実にルーズに考えていたこと一つ見ても、実に緊張感のないさまがありありと感じられる。後にこの緊張感の無さがとんでもないことを引き起こすことになろうとは、このとき考えも及ばなかった。
リュックを背負い、イタリア製の登山靴を履くととたんにやる気が出てきた。私は少しずつペースをつくるように歩を進めた。舗装された道はあるところで林道へと変わり、そのちょうど変わり目の所に机が置いてあり、入山者の名前を記すノートが置かれてあった。それをひもといてみると実に大勢の人がここに訪れていることが分かった。自分もその一人なのであることを確かめるようにノートに名前を書いた。そして、何げなくページをめくると10月10日の項に「この先、昇龍の瀧近辺で熊が歩いていた」趣旨の記録が目に入った。昇龍の瀧とは、この先林道の終点からさらに奥に入った所にある見事な瀧のことで、私もそこで一休みしようと考えていた所である。一瞬、背筋に冷たいものが走った。
もしかしたら今日、その熊に出会うかもしれない。季節は秋口、すでに晩秋と言っても良い。この時期の熊は、冬に向かって食いだめしなくてはならず、食欲が旺盛で人里にさえ顔を出すと言う。熊は本来憶病であり、人間が住む里には滅多に下りてこない。でも、食欲が旺盛になった熊は、その恐怖に打ち勝って里に下りてくる。当然、緊張しきっているので、ちょっとおどかしただけでパニックとなる。パニックになると誰彼かまわず襲ってくる。それが熊との出会いにおける襲撃事故となるのである。
私は腰に括り付けていた430MHz帯のトランシーバーのスイッチを入れた。
熊は非常に憶病である。だから、匂いや音に敏感だ。東北地方のある村では、熊が出没する地区の小学生に鳴り物を持たせると言う。その中には大きな鈴をランドセルに付けて歩く子供もいるそうだ。私の友人も北海道を旅していた時に、腰に蚊取り線香を付けて山に登った話をしてくれた。地元の人たちによれば熊は蚊取り線香の匂いを嫌がるとか。だから、地元の人たちも熊がいる山に入るとき、携帯用の蚊取り線香入れを持ち歩き、熊の出そうな所へくると、蚊取り線香に火をつけるそうである。真偽の程は分からないが、友人は蚊取り線香を付けて大雪山に登ったそうだ。それが本当に利いたかどうかは定かではないが、取りあえず無事に下山してきたのだから少しは効き目があったのかもしれない。
私は音で対策をとることにしたのだ。鈴の音でさえ嫌がるなら、トランシーバーから出るあの甲高い人の声ならばもっと嫌がるだろう。慣れている人間でさえ、長時間あの甲高い声を聞いているとさすがに嫌気がさすくらいなのだから。
でも、さすがに早朝だから誰の声も聞こえてこなかった。仕方がないのでスケルチを開いてホワイトノイズを出してゆくことにした。ボリュームを最大にしておけば良かろうとの判断だった。
ザーザーと言った雑音を響かせながら、私は林道を歩いた。約十分ほどで昇龍の瀧についた。この手前で林道は消えていた。
昇龍の瀧は実に美しい滝だった。水量、姿も申し分がない。休憩のために滝のそばまで寄って腰を下ろした。既に、額には汗が滲み出ている。腰にぶら下げたタオルで汗をぬぐい、大きく深呼吸した。心地よい一瞬である。でも、先ほどのノートが気になった。熊が歩いていたとはこの滝の近辺なのである。回りを見回したがそんな気配は毛ほども感じられない。大丈夫だ。そう確信した。
そのうち一人の登山者が私を追い越していった。滝の側で休憩している私を見つけると軽く頭を下げて会釈をした。私も頭を下げた。これがいいのである。都会では見ず知らずの他人に挨拶をすると言う習慣はない。しかし、山では違う。見ず知らずの人とは言え、お互いに挨拶をするのがしきたりだ。それによって、妙な連帯感を感じるのだ。「ああ、この人も頑張っているな。」「同じ仲間なんだな。」という仲間意識がたまらなく心を安心させるのである。
これでよい。これで熊は完全に出なくなる。一人ならば出くわす可能性があるが、複数になればそれだけ頻繁に気配がするので熊は、人の歩く道を避けるようになる。私は安心して登れるようになった。
それから暫くして私は滝をはなれ、本格的に登り始めた。道は緩やかに滝を巻くようにして続き、沢を渡ると岩がところどころ顔をのぞかせている所を登るようになる。道も岩や石がごろごろとしている道だ。スニーカーや運動靴のような底の薄い靴だと足の裏が痛くなってしまうだろう。登りもしだいにきつくなってゆく。体力に自信のない私は焦らずじっくりと登っていった。次々と登山者が自分を追い越してゆく。足も速い。実は私が遅すぎるのだが、そんなに焦る必要を感じていなかった。私は気楽にマイペースで登っていった。そして、息苦しくなるとそこは躊躇なく休んだ。
道自体は小さな岩が露出しているような道で歩きやすい。ぬかるみだとか、ヤブがひどく、歩きづらいと言うことはなかった。ただ、ところどころに急な登りがあり、そのたびに気が滅入ってしまうぐらいだ。
やがて、登りの中間点である御手洗場(みたらしば、と読む)のあたりから登りは最高に厳しくなった。見上げるばかりの急角度の斜面をジグザグに登ってゆく。道のところどころには岩場があり、それを巻くように登ってゆく。中にはクサリ場もあった。
大きな岩場を2回ほど巻くようにして登り、登り切った所が一位のガタワと言う所である。ガタワとは峠の意味らしい。確かに峠であった。小さな社があって、石像がまつられていた。ここから北の方に下ると清滝小屋という山小屋に行ける。しかし、今日の目的は山頂にあったので北へ下る道はとらず、左に続いている山頂への道をとった。
それはまた、急な道の連続だった。左側には間近に梵天尾根、遠くには奥秩父の山々が見えている。それらを眺めながら岩場の狭い道をたどってゆくとクサリ場に突き当たる。すでにアンテナポールを杖代わりにしていた私はふと困った。登るためには手に持っているポールが邪魔なのである。でも、クサリ場自体よくみるとそんな急な斜面ではない。ポールを持ったままでも登れそうだった。はたしてその通りだった。ポールは邪魔にならず、バランスよく体を保てばべつにクサリなど不要だった。

再びジグザグに斜面を登る。その道は、登り初めの頃の道に比べると岩が露出している所が多く、その岩に大木が取りつき根を張り、道自体が階段状になっていた。暫くして再びクサリ場に出くわした。
今度のクサリ場は岩自体が滑らかでホールド(足掛かりや手掛かりのこと)がなく、文字通りクサリでないと登れない所だ。クサリ場のてっぺんでは、おばさんたちのパーティが、クサリを使って下りようとしてもがいているのが見えた。ポールを持ったまま登ろうなんて事は到底無理だった。
ところがふと脇を見ると狭い踏み跡らしきものが見えた。もしかしたら、この岩を巻いて登っているかもしれないと思った私は、その踏み跡をたどってみることにした。案の定それは急な道ではあったが岩場を巻いている道であり、登り切ると岩場の上の道に出た。振り返ると先ほどのおばちゃんパーティが、クサリ場をはしゃぐような声を上げながら一人一人下りていくのが見えた。
最後の一人が下りたのを確認してから再び、その道を歩き出した。
それは相変わらずの急登だった。登り続けると今度は鬱蒼とした森の中に入っていった。道も緩やかな登りになり、梵天尾根や奥秩父の山々も見えなくなるといきなり、目の前に建物が見えてくる。それが「両神神社」である。神社の前には長椅子があり、休憩できるがさらに進むと避難小屋があり、その先には休憩できる場所があるのでそこで休んだ方が正解であった。ここまで来るともう山頂が目の前に見えてくる。
休憩場所からは梵天尾根や西上州の山々も展望できる。実に素晴らしい場所だ。山頂に登っている人の声も聞こえてくる。あと一歩で山頂だ。そんな気さえしてくる。
そこから一旦下る。約10メートルくらいか。すると水場に向かう道との分岐点に来る。水場まで200メートルという標識が立っていた。そろそろ水を補給したほうがいいかなと思い、水場に向かって歩き始めた。ところが、途中でアベックに出会い、どういうわけか水が湧き出ていないと言っていたのであきらめて戻ることにした。時間も予定より大幅に遅れており、このままでは山頂にいる時間さえなくなってしまう可能性もあったし、さすがに疲れを感じていたこともあって山頂への道を急ぐことにした。
水場への分岐からさらに緩やかな斜面を登っていくと、またクサリ場が見えてきた。しかも、その上からは人の声が聞こえてくる。どうやら尾根道があるらしい。頂上はもうすぐだ。
目の前のクサリ場はほとんど直登に近いものがあった。ポールを持っては登れそうもない。それに周囲を見回したが巻き道さえ見当たらなかった。ただ、すぐ右隣の岩場が、比較的ホールドがしっかりしており、都合のいいことに小さな棚状の出っ張りがいくつかあった。ホールドの状態から見て、フリークライミングの経験がない私にでもよじ登れそうであった。こうなったらポールをまず上段の棚状の岩場に取りあえず置き、体を上段に移動させてからさらにうえにポールを持ち上げるといった手法をとることにした。岩場と言っても5メートル程度の低いものだからできる手法だ。
それでも私にとって岩場登りは経験の浅い手法である。規模は小さいとは言えフリークライミングであることに変わりはない。友人で山登りを趣味としているのがいるが、彼によればバランスがすべてだという。3点確保が基本中の基本だ。
まさによじ登ると言う表現が当たっている。今回の山行はよじ登ることが多いなとぼやきながら慎重に登った。この後、この言葉を体全体で味わうことになる。
岩場の上はすぐ尾根道だった。そして目の前には山頂が見えた。岩場一つを越え、山頂に立ったのは11時25分だった。登頂開始から実に5時間が経過していたのだ。

山頂の展望は素晴らしかった。梵天尾根の向こうに奥秩父の山々が見え、振り向くと西上州の山々が手の届きそうな所に見えていた。その向こうには、うっすらと浅間山まで確認できた。特に感動したのは、奥秩父の山々の向こうに、白く雪化粧した富士山が見えたことだ。私は幼い頃より富士山を見て育ったので、富士山に対しては特別な思いがあり、このようにはっきりと確認できたことが嬉しかったのである。
小さな社の裏に展望のきく場所があり、そこでさっそく昼食タイムをとった。ポカリスエットで登頂成功を祝う。山に登り切った後のポカリスエットは格別のうまさである。
ちなみに、そのときの山頂は実にたくさんの登山者でにぎわっていた。山頂自体はまさに岩場の上にあり、広さはそれほどなく、10人もいると山頂に登ることはできないなと感じるほどの狭さだった。
昼食を終えてさっそく第二の目的である無線交信を始めた。今回の山行はきつい登りが多く、途中で帰ろうかと思う事しきりだったが、それでも頑張ってこられたのはこの無線交信をやりたい一心だったからである。無線交信の醍醐味はまさに遠くの局と交信すること。さらに、多くの局と交信することである。そして、遠くの局と交信するには高い山に登るのが一番だ。さらに、数多くの局と交信するには、誰でも楽に行ける山では駄目だ。そういう所は既に多くの人が登って交信しているはずで珍しさがなく、むしろ、あまり人が登らない山の方が珍しさも手伝って多くの局に呼ばれることになり、短時間でたくさんの局と交信できることになる。両神山はその中では比較的珍しい山の一つに分類される。というのは登山口までのアプローチが長く、交通の便が良くないこと。さらに、山自体がなかなか険しいため、重量物を運び上げるのになかなか苦労させられるからである。
たくさんの局に呼ばれると何故か、たくさんの人に注目されたような感じがして実に気持ちがよいものだ。これを無線仲間の間では「パイルを受ける」といい、「パイルを受ける」ことは非常に名誉なこととされている。逆に、どこからも呼ばれないと非常にみじめな気分になるものだ。
アンテナを組み立ててポールに固定し、さっそく交信を開始した。思った通り短時間であったが様々な局と交信が出来た。自分の地元では交信が出来ない遠方の局とも交信が出来た。この分野での目的は達成できた。まさに大成功だった。
後は下山すれば良いだけであった。
山頂から下山するルートはいくつかあった。まず、山頂から北へ向かって志賀坂峠へと下りるルート。これは八丁尾根と呼ばれる高低の激しい岩尾根を経由することになる。八丁尾根はガイドブックによれば「健脚向きコース」となっており、多少の岩登りの技術を必要とすると紹介されている。私の技術はそれほど高くないし、第一戻らねばならないのは白井差の山小屋だ。その前には私の愛車が待っている。
山頂から南へは、あの梵天尾根が延びている。そして、その途中にある大峠からは、白井差の小屋までの道があった。
そして、もう一つのルートはもと来た道を戻るというものだ。なんていったってこれが一番早いルートである。
私はここまできて迷っていた。それと言うのも、私には変な趣向がある。というのは、一度の山行で「一度通った道は二度と通りたくない」というものだ。単にへそ曲がりだといえばそれまでなのだが、どういうわけか山を歩くとき必ずといっていいほど私はループを組むのである。そうすれば、一回の山行でいろいろな場所の景色を堪能できるし、第一それが楽しいと感じるのである。同じルートを往復するのはなんか勿体無い感じがするし、マンネリのような気がしてどうも好きになれない。道がないのであれば仕方がないが、あるならば例え少々遠回りになろうともその道を歩きたいと思うのである。
だからこの時、最後まで迷っていたのも「梵天尾根から大峠」に向かうルートに「未練」を感じていたからに他ならない。でも、早く下山する目的からいえば、「一位のガタワ経由白井差の小屋」ルートをとるべきであった。
結局この時は誘惑に勝てず、「梵天尾根から大峠経由、白井差の小屋」ルートをとった。地図からみて3〜4時間で白井差の小屋に着けそうであるし、道もほとんど下る一方で多少の遅れが生じてもすぐ取り戻せると思ったからである。
しかし、これには大きな誤算があった。既に白井差から頂上へ登る事によって、体は疲労していたのである。でも、浮かれていた自分には冷静に判断する余裕がなかった。むしろ、なんとかなるだろうとの油断さえあった。それが、「梵天尾根から大峠経由、白井差の小屋」ルートに固執する結果となったのだ。
山頂を出発したのは午後2:30分。ここでも予定より30分遅れての出発となった。無線交信が成功したのでなかなか止められずにいたからだ。でも、下りには自信があった。30分の遅刻ぐらい、いずれ取り戻せるだろうとタカを括ってもいた。梵天尾根は明るく緩やかな尾根だからと思い込んでいたふしがある。
山頂を下りて一位のガタワへの分岐に戻ると、梵天尾根への道をたどった。確かにそこは明るい尾根道であった。既に紅葉は終わり、葉もすべて落ちて道に敷き詰められている。色とりどり枯れ葉の絨毯だ。さくさくという踏み音も軽やかに、私は尾根道を下っていった。地図で確認するとこの先には急な坂があるようだ。でも下りである。たいしたことはない。
やがてその坂が見えてきた。恐ろしく急な斜面をジグザグに下っていく。高度も見る間に下がっていった。やがて目の前にピーク(尾根の高まりのこと。頭ともいう)が圧倒的な迫力で前に立ち塞がってきた。
その急な坂を下り切ったとき、私は自分の足に萎えが生じているのに気づいた。ひざ頭がぶるぶると震えているだけでなく、太ももに力が入らなくなっていたのである。だから、目の前のピークが絶望的な高さに思えた。
そこはヒゴノタワと呼ばれるコル(鞍部)であった。そして、目の前にあるピークはミヨシ岩と呼ばれている岩が存在すると言われているピークである。これを越えないと大峠にはたどりつけない。振り返ると今まで下ってきた急坂のある尾根が、さらに圧倒的な高さでそびえているように見えた。進むのは嫌だったが、戻ることはできない。あの、下るのさえ大変だった急な道を、逆に登っていくなど今の萎えた足では不可能なことだ。
結局進むしかなかった。
足の萎えは深刻だった。ポールを杖代わりにして一歩一歩登るが、すぐに息が上がってしまう。五メートルも登ったろうか、たまらず木の根っこの隙に腰を入れ、へたるようにして座り込んでしまった。もう動けない。動く力がなかった。
木々の隙から空を見る。いつの間にか空が曇ってしまっている。時計を見るとはや四時を回っていた。すでに一時間あまりが経過していた。地図上の距離では既に大峠に到着していなくてはならない。だが、今はまだその手前のヒゴノタワでうろうろしているのだ。しかし、不思議と焦りという感覚がなかった。ただ、この一山を越えれば大峠だ。そこまで行くことが出来ればよい。懐中電灯は持ってきているし、いざとなれば夜道もできる。それだけを考えていた。いや、それだけを考えることで焦りを隠していたのかもしれなかった。
とにかく休むことだ。休めば体力が回復する。そして、落ち着くことだ。心が落ち着いたら歩こう。そう考えた。
すると、周囲の景色が目に入るようになる。ヒゴノタワは地図によれば一千四百メートルにみたぬ高度にある。今はそのヒゴノタワを見下ろせる所に座っている。高さはだいたい十メートルぐらいか。だから、自分がいる所は一千四百メートルの位置にいるのかもしれない。なんとなくそう考えた。
紅葉のシーズンも終わり広葉樹はすべて葉を落としていた。だから、向かいに対面する尾根の姿がよく見える。その尾根の向こう側に、今日登ったはずの両神山山頂があるはずだった。
峠とは山と山の間にある鞍部を指すが、そこはまた風の通り道でもある。谷から吹き上げてくる風が自分の目の前を通り過ぎていくのがわかる。それは歩き続けて汗をかいた体には心地よかった。心地よいなと思いながらも、これが冷たく感じるようになったら危ないなと、漠然と考えた。
ふと思い出したようにポケットから飴を出した。疲れた体には甘いものが良いと聞いていたので、ポケットに入れておいたのだ。さしずめ、単独行の登山家・加藤文太郎ならばウィンドヤッケに入れた甘納豆だろうな、などと昔読んだ小説(孤高の人・新田次郎著)の主人公に自分をなぞらえて苦笑した。
飴を口に放り込むとつばきが出る。まだ水の補給はいらないなと、とっさに判断した。既に、持っている水筒の水は半分程度になっているし、水を飲み過ぎると疲れが増す。今は我慢だった。
両足の太ももを軽く叩いてマッサージをする。少しでも疲れを癒したかったからだ。頼みになるのは自分の足だけ。足だけなのだから。
暫くすると汗が引いた感じがした。歩こう。歩かねば。私は立ち上がった。両足に僅かではあるが力が戻っていた。しかし、以前のような力強さはない。私はこの時初めて「遭難」の二文字を意識した。より明確に言えば浮かんだ言葉は「疲労凍死」であった。
既に全身は汗でびっしょりであった。これが冷えきれば充分死ねるのである。高山でタブー視されているのは水に濡れていることだ。水は蒸発することにより、急速に体温を奪ってゆく。体温を失うと、体の動きは鈍る。動きが鈍ればさらに体温が下がる。その魔のサイクルの行き着く処は死だ。
でも動けるうちは大丈夫。適度に動けばその魔のサイクルに落ち込むことはない。大丈夫。まだ歩けるから大丈夫と自分に言い聞かせていた。言い聞かせながら、目の前のピークを越えることに専念した。
坂は急だった。ところどころ道を見失ったが、そのときは斜面をよじ登った。よじ登ると道が見つかった。こういうときに谷の方に下ると余計危険だ。完全に迷子になってしまう。ただひたすらに「このピークを越えれば大峠だ。後は下りなのだ」と呪文のようにつぶやきながら登っていった。
その目の前にクサリ場が現れた。しかも、ピークはさらに上だった。ため息が出た。しかし、登るしかなかった。ポールを先に押し上げ、鎖を両手で持ち、足をホールドに乗せるようにしてよじ登る。距離にして五〜六メートルだろうか。長い登りだった。やっとの思いでクサリ場を抜けた。しかし、ピークはさらに上だ。恨み言が口について出る。恨んでも仕方のないことなのだが、恨み言を言うしかなかった。
さらに一歩一歩道を踏み締めるようにして登ってゆくと、大きな岩のようなものが見えてきた。その岩をよじ登るといきなり視界が開けた。ここがミヨシ岩である。中津仙峡や奥秩父の山々が泰然自若として存在していた。美しい展望だった。私はピンチの状態など忘れて見とれていた。
空は曇っており太陽の位置は確認できなかったが、時計から察するに既に日の入りの時刻であった。ぐずぐずしては居られなかった。
ルートは岩を縦走しているようだった。黄色いペイントが方向を指し示している。ポールを杖代わりにしながら岩の上を歩いていった。両側は絶壁である。手すりなどはもちろん存在しない。しかも三百六十度の展望が利く岩場だ。でも、不思議と恐怖は感じなかった。
岩場の上を歩いてゆき、さらに小さな岩を巻くように進むと二本の板を渡しただけの橋を通り過ぎた。さらに進むと今度はクサリ場の下りになった。ほとんど絶壁だ。覗き見ると、ところどころに踊り場が確認できる。でも、ポールを持っては下ることが出来そうになかった。やむを得ず、ポールを先に投げ落とし、クサリを両手で持って下りることにした。一段一段慎重に下りていった。ポールも二回ぐらい投げおろした。なくなっては困るので、踊り場に掛かるよう慎重におろした。
かなり下ったろうか。やがて鞍部の道が見えた。でも大峠ではない。地図によればまだピークが一つあるのだ。このピークを過ぎれば大峠なのだと自分を励ました。このころから足の萎えは尋常のものではなくなっていた。次のピークを越えたらば足が動かなくなってしまうかもしれないと思えるまでになっていた。
思った通り、その先には大きなピークがあった。これを越えれば大峠だ。頑張ろう。
空は急速に暗くなっていた。足は時間とともに萎えていくのがわかった。動かなくなるのも時間の問題だなと感じていた。歩いては休み。休んでからまた歩く。何度それを繰り返したろうか。とにかく疲れたら休むことだ。休んで少しでも足の回復を図ることが大切だと自分に言い聞かせていた。
やがてピークは過ぎて下りに入った。そしておぼろげながら標識が見えた。標識には白井差と書かれているのが読めた。もう安心だ。ここを下れば大峠だと思うと嬉しかった。とうとうここまできたか。ここで一服しよう。リュックを肩から下ろして道端に座り込み、地図を広げた。距離を追うと確かにピークを越えている。もう大峠だ。
足の回復を図り、暗くなってゆく空を見上げながら、白井差小屋の前に止まっている愛車を思い出していた。あれが自分のベースキャンプなのだ。あそこに戻れば自分は助かるのだと自分に言い聞かせた。
標識から先は下りになっていた。かなり急な下りだ。ほとんど階段状態の下りだ。しかも、近ごろ建てられる建売住宅の階段よりきつい。下ると言うより落ちるという表現の方が当たっている。萎えている足にはこたえた。膝頭はカクカクと震えるし、気持ちも怖じ気付いている。気持ちは先へと急くが、体が思う通り先に進まないのだ。下手をすればそのままごろんと落ちてしまう。
やがて鞍部が見えてきた。やった!大峠だ、と思った。しかし妙だ。標識らしきものが一つしか立っていないのである。大峠ならばもう一つ、白井差の小屋を指し示すものがあるはずだ。それは進行方向を指すもの、一つしかなかった。そして、その標識が指す方向には不気味な一つのピークが見え出していた。
標識の前まできた。やはりそれは、大峠を指し示していた。まだ、大峠ではない。足がガクガクと震えているのがはっきりとわかる。まだまだ先だった。
でも道はそのピークへと向かっていなかった。ピークの左側方に向かって下っている。どうやら巻き道のようだ。ぐるっと回ってピークを避けているのだろう。そうだ、そうに違いない。私は気を取り直してぶるぶると震える足を引きずるようにして道を下った。
しかし、その先に絶望的なクサリ場があった。よく見るとほぼ直角のクサリ場だ。皮肉なことにその高さは、今回の山行で登ったクサリ場のうちでは最大級のものだった。
おもわず私は悲鳴を上げてしまった。「なんだよ、まだ登らせるのかよ!いったいいつになったら大峠に着くんだよ!」と。
私は暫くその場で行ったり来たりしていた。立っているだけてぶるぶると震えるほど萎えている足で、この岩場をよじ登れるかどうか自信がなかったのだ。時間だけが無駄に過ぎていく。既に薄暗がりと言ってよかった。色の判別さえもつかない。今こうしてその時を思い出そうとしても、残念ながら白黒のイメージしか思い出せない。
暫くの躊躇の後、思い切って登ることに決めた。いや、登るしか手はなかった。このままここにいても状況は変わらない。野宿するにも用意はない。11月とは言え、山の上では冬だ。しかも着替えさえろくにない状態で野宿しようものなら、汗で濡れた体だ。凍死しないとも限らない。
リュックをおろすと、今まで杖がわりに持っていたポールを括り付け、両手をフリーにした。
今度のクサリ場は巻き道もなくホールドも小さい。高さも五〜六メートルは軽く越えている高さだ。しかも角度は急だ。ほとんど直登と言っていい。クサリを握りしめながら息を整えた。時間は切迫している。これ以上暗くなったら道に迷う恐れがあった。
今はこの萎えた足だけが頼りだ。クサリを握りしめる手が震えた。息を止め、クサリを思いっきり引きつけ、足をホールドに引っかけると力一杯踏み締めるようにして登った。足は激しく震える。リュックの重みが肩に食い込む。気は急くが体は思ったように動かない。まさによじ登るという感覚だった。
今日という日はなんて言う日だ。よじ登るという行為を何度となく繰り返す日だ。しかも、よじ登れば登るほど、より大きな岩場にチャレンジしなくてはならないとは…。正直なところ、こなければ良かったとさえ思っていた。
やっとの思いで岩場を登り切った。登り切って地べたに座り込んだ。そして、良くぞもってくれたと太ももをなでた。しかし、もう階段の一段でさえ登れないだろう。ほとんど足の力を使い果たしたと言って良かった。
岩場の先は緩やかな下りだった。ピークは越えていないが、この岩場自体、ピークを避けて道をつけた結果、設けたような作りだったのである。ピークを巻いてずんずん下ると薄暗がりの中で三方向に矢印のある標識が見えた。ついに大峠に着いたのである。
大峠には休息用のベンチと机が設けられていた。明るかったならばここで腹ごしらえをして行けそうな場所だ。案内板が立ててありコースも載っている。しかし、既に忍び寄る夕やみで字が読めない。時間は既に午後5時半をまわっていた。
小休止もそこそこに私は出発した。尾根道を左に折れ、急な斜面をジグザグに下ってゆく。尾根道とは異なり鬱蒼とした木々に埋もれ、道が良く見えない。かろうじて判別する道を急速に下ってゆくと、やがて水の流れる音が聞こえてきた。下小屋の沢である。
ここで私はふと朝のノートのことを思い出した。昇龍の瀧に現れた熊のことである。沢沿いに歩いていったら熊に出会うかもしれない。暗がりで熊に出会おうものなら大変なことになる。とたんに恐怖が襲ってきた。
私は腰にぶら下げていたトランシーバーのスイッチを入れた。ザーっという雑音が静かな谷間に響いてゆくようだった。すでに風もなく、音と言えば時折風に吹かれて落ちる枯れ葉の音と、沢に流れている水の音だけである。あとはなにも音がしない。
430MHzの電波も谷間には届かない。今となっては人の声が聞きたいと思ってもなにも聞こえない。せめてラジオでも持ってくれば良かったなと思った。
水辺の近くまできてそこでリュックをおろした。懐中電灯を取り出して音のする方を照らすと小さな湧き水のような流れがあった。懐中電灯を近くに置いて流れを照らし、それをまたいで両手のひらで水をすくって飲んだ。五杯ぐらい飲むと気分が落ち着いた。かなり緊張していたようだ。でも、まだまだ安心できない。小屋まではさらにここから1時間余り、とにかく歩かねばたどり着けないのだ。
周囲は既に闇の中と言って良かった。懐中電灯の光りが照らすところ以外はなにも見えない。振り仰ぐと木々の隙にわずかながら空が見える。しかし、それも僅かな明るさしかなかった。時計をみると大峠を出発して20分がたっている。あとこの三倍は歩かねば白井差の小屋には着かない。まだまだだった。
リュックを背負って歩き始めた。ポールを杖の代わりにしてゆっくりと歩く。懐中電灯の明かりで道の先を照らしながら、方向を確かめながらゆっくりと歩いていった。足の萎えはひどく、ほんの数メートルの登りでも動けなくなる。歩けなくなったらそこは躊躇なく休み、再び歩く。とにかく、全身の力を振り絞るようにして前へ進んだ。こんな大変な山行は生まれて初めてだった。
そういえば、中学校の修学旅行のときも、こんな苦労をしたな。歩きながらそんなことを思い出していた。
私の出た中学校は、神奈川県にある公立の中学校だった。横浜市立瀬谷中学校と言った。中学校の修学旅行と言えばこのあたりは京都と相場が決まっていたのだが、私の通った頃の瀬谷中には、その頃としてはかなりやり手の教師が集まっていたらしい。先生たちは、京都なんか行くよりも別の、もっと自然の美しいところでじっくりと勉強をさせたいと考えたとか。結局それによって選ばれた場所が「信州八坂村と白馬八方尾根」だった。どうやら、瀬谷中の先生方は当時としては先見の明があったようだ。
そのなかで特におもしろいのが八坂村での「体験学習」だった。つまり、総勢八クラス約400名にならんとしている生徒をいくつかの「班」にわけてテーマを決めて体験学習をさせると言うものだ。考古・地質・炭焼き・昆虫・スケッチ等々にわかれ、それぞれが自分の好みで選び、学習が出来た。
その中で私は「地質班」を選んだ。理由は大したことではない。「地質班」ならば「化石掘り」が出来るからだ。私はまだ「化石」を手にしたことがなかった。どういうものが見てみたかったからだ。
しかし、現実は厳しいものだった。化石の出る場所は山道を越えていかなくてはならない。しかも、当時私は典型的な肥満児であり、極めて体力がなかった。普通の中学生なら一山軽く越えて行けるのに、私はばてにばててしまい、途中から村に戻ることになってしまった。子ども心に情けなく、一緒に戻ってくれる村の人も、私の堪え性の無さにあきれ果てている様子だった。
まさに今の状況と同じだ。ただ、異なるのはあのときはまだ、村の人が脇に居て一緒に村に戻ってくれたが、今は独りぼっちであることだ。つまり、励ましたり助けてくれる人が近くにいないと言うことなのである。ここで死のうが、見取ってくれる人さえ居ない。これほど侘しいことがあるだろうか。よく「山が好きな人は、山で死ねて本望」などと言われるがあれは嘘ッパチだ。山だろうが街だろうが、誰もいないところで死ねば、それはたんなる「野たれ死に」である。「野たれ死に」なんぞ誰が望むのか。少なくとも自分は望むもんか。何としても戻ってやる。そう考えた。
沢と平行に道は続いた。時には離れ、時には交差しながら、ほぼ下りの状態で延々と続いていた。どれくらい歩いたろうか、ふと再び道が登りにさしかかったように見えた。
その時の私にとって、登り=絶望とさえ言えた。足が萎えている今、登ると言う作業には非常に努力が必要とされた。おかしい。地図では登りなんてないはずだ。道を間違えたのか。そう考えたほどそれは衝撃的なことだった。
でも地図をよく見るとなるほど、僅かではあるが白井差の小屋に行く途中に、登りらしきところが一ヶ所だけあった。地図で見る限り高度差は20〜30メートルぐらいだ。大した事はない。私は登ると決めた。
普通の体力ならばそんなに苦労はしない緩やかな登りだったが、今の私には過酷過ぎる登りだった。幾度となく小休止をしながら坂を登り切るとやがて緩やかな下りとなった。いつの間にか沢の音が遠ざかり、それまでの雑木林が杉だろうか、人工的につくられたもののような真っ直ぐな幹のものに変わっていた。
さらに行くと何本か巨木が立つ広い場所に出た。懐中電灯で回りを照らすと神社の境内をおもわせる小さな広場だった。同時に道を見失ってしまった。足元には巨木の根が八方に広がり、どこまで言っても道らしきものが確認できない。しかたなく、もと来た道を戻ると小さな祠が目に入った。その前あたりにようやく道を見つけた。ここを行けばいいのかと思い、その道をたどることにした。
その時である。その道の行く先に、青白い小さな光が目に入った。正直言ってどきりとした。ひとだまか、と思ったからである。でも、その光は動かなかった。道のはるか先でじっと動かないでいた。
よく見るとそれは、道の先に森が開けているところがあり、そこから向かいの尾根がうっすらと見えているのだが、その麓にある何かの光だったのである。
私にはハッキリとわかった。ついに白井差の小屋を見下ろせる尾根に出てきたのである。その青白い光とは白井差の小屋の灯りだった。やった、ついにここまでこられたのだ。はやる気持ちを抑えながら私は、道を歩く速度を上げた。
その道も急な下りだった。クネクネと巻きながらズンズンと高度を落としてゆく。萎えた足にはきつい下りだ。でも、既に目の前に白井差の小屋の灯りが見えている。あとはその灯りを目指してくだるだけ。萎えた足にも力がよみがえるようだった。
でもさすがに疲れた。額の汗が流れて目に入る。鉢巻きのようにしていた手ぬぐいも、汗を吸って濡れていた。丁度、腰掛けるにいい岩場を見つけたので休むことにした。見晴らしは良い。白井差の小屋の灯りもすぐそこに見えている。焦る必要はない。じっくり、確実に進めばいい。なんとなく、あそこまであと20分位だと直感した。
事故は油断より起こる。ゴールが目の前となっている今こそ、より慎重に事を運ばなくてはならない。今度の休息は充分とったほうがいいだろう。
風は吹いていない。空は曇っているので星は見えない。かといって雨が降る様子もなかった。私は全身の力を抜き、岩に体を預けるようにした。やっとだ。やっと、白井差の小屋に着くのだ。私は今回の山行を振り返った。
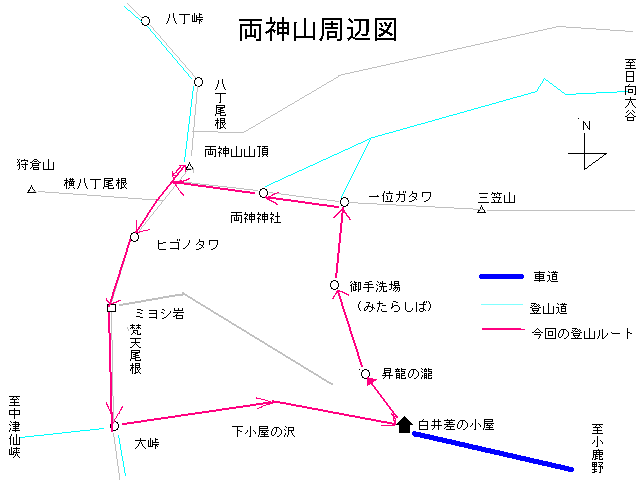
今回の山行の誤算は一つ。体力の計算が甘かったことだ。登りを慎重に計画した癖に、下りに関しては実にいい加減であったこと。これである。たしかに登りより下りの方が簡単であり、楽なのではあるが、かといって全然体力を消耗しないわけではないのだ。今回の両神山のような険しい下りの場合は、下りでも登りに負けないくらい体力を消耗するのである。それを改めて確認させられた。
さらに私自身、初めて歩く山をナメていたことである。確かに昨今、優れた地図やガイドブックなどがあり、ある程度はその山を知ることが出来るようにはなった。しかし、やはり現実にはその山を実際にその目で見、体で感じなくては分からないことがあると言うこと。そんな当たり前なことを、私自身見失っていたと言うことがよく分かった山行だった。5万分の一の地図では、20メートルに満たない高低差は現れてこない。こんな基礎中の基礎さえも忘れてしまっている。このような状態で山を続ければいずれ取り返しのつかないことを引き起こしたに違いないのだ。
初めての山行に目的を二つ持ってしまったことも失敗の要因と言えた。無線と散策、どちらか一つに絞るべきだったのである。無線をやるのであったら、最短距離で下山すべきであった。つまり、大峠など寄らずに、一位ガタワを経由して昇龍の瀧の前を通り、白井差小屋へ至る道を選ぶべきだった。ならば、道の具合、距離感などが予め読めるから、もっと楽に早く下山出来たに相違ないのだ。
そう思うと私は両神山に感謝したくなった。忘れていた基本を思い出させてくれたのである。私は下手に山に慣れてしまい、とんでもない登山者になってしまうところだったのだ。
私は自分を奮い立たせるつもりで歌を唄うことにした。「紅の歌」という力強い歌だった。歌うと体の奥から元気が出てきた。その元気で最後の下りを一気に下ってきたのである。
白井差の小屋の背後から私は下りてきた。小屋の庭先をトコトコ歩き道に出ると、朝には2〜3台あったはずの車も、今は自分の愛車1台だけになっていた。
車のトランクにリュックを乗せて肩から下ろすと、改めて全身が疲労困憊していることがよく分かる。両足の脹脛もパンパンで、力をちょっと加えるだけで筋肉がつりそうだった。
リュックから水筒を取り出すとまず、残っていた水の半分を道に撒いた。山に供養したのである。そして残った半分を一気に飲み干し、無事下山出来たことを山に感謝し、祝ったのである。飲み干した水は家から持ってきた水道の水であるが、今まで飲んだどの水よりもうまく感じた。
そして、朝も開いた入山者名簿に次のように記録した。
「午後六時二十五分下山。バカヤロー 大峠なんぞ寄ってたら日が暮れちまったよ。」
この時の私の正直な気持ちだった。
私は今回の山行で、様々なことを学ばさせてもらった。それを忘れないようにするために、この山行の経緯をここに記録しておこうと考えた。自然を甘く見る人間は、自然によって痛烈なしっぺ返しが来る。こんな当たり前のことでさえ、慣れてくると忘れてしまうものだ。その時はもう一度原点に戻らなくてはならない。
今はもう、両神山なんて登りたくないと考えているが、それもここ暫くのことだろう。そのうち、再び登りたいと考えるに違いない。その時はもう一度、この記録を読んで、自分自身を戒め、改めて覚悟を決めた上で計画を立てようと考えている。
リュックをトランクに詰め込み、登山靴を脱いでスニーカーに履き替えるとエンジンキーを入れ、エンジンを動かした。エンジンが軽やかに動き出すとギヤを入れハンドルを操作して、暖かいわが家目指して白井差の小屋をあとにした。
完
戻る